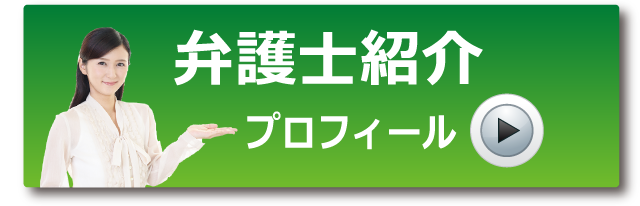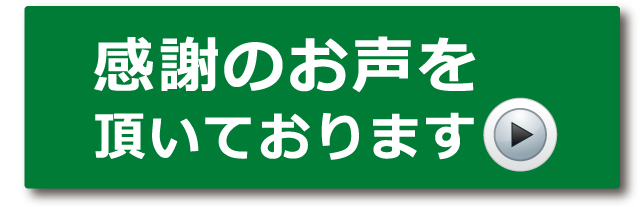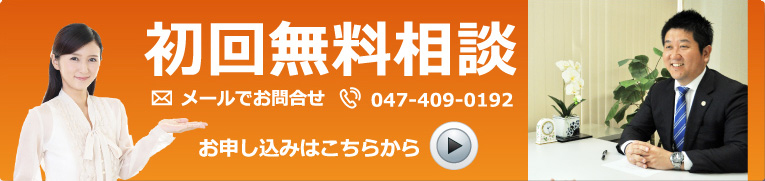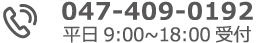![]()
その他訴訟


当事務所の弁護士は、上記には分類されない種類の裁判も多く手がけております。トラブルの具体的内容は一人一人異なることから、相談者の具体的事情を検討し、これを踏まえた、最適な解決策と見通しを助言致します。ご遠慮なくご相談ください。

その他訴訟に関する弁護士費用
●金銭請求(税込価格)
経済的利益の金額
300万円以下の部分
〇着手金 8.8%(最少額110,000円)
〇報酬金 17.6%(最少額220,000円)
経済的利益の金額
300万円を超え 3000万円以下の部分
〇着手金 5.5%+99,000円
〇報酬金 11%+198,000円
経済的利益の金額
3000万円を超え 3億円以下の部分
〇着手金 3.3%+759,000円
〇報酬金 6.6%+1,518,000円
経済的利益の金額
3億円を超える部分
〇着手金 2.2%+4,059,000円
〇報酬金 4.4%+8,118,000円
(税込価格)
| 経済的利益の金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8.8% (最少額110,000円) |
17.6% (最少額220,000円) |
| 300万円を超え 3000万円以下の部分 |
5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
| 3000万円を超え 3億円以下の部分 |
3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
| 3億円を超える部分 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)
| 〇差出人がお客様名義の場合 | 33,000円~ |
| 〇差出人がお客様名義の場合 | 55,000円~ |
(税込価格)
 当事務所で取り扱った
当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例事案の内容等については、
一部改変しております。
その1病院側の過失により依頼者の父が死亡し、病院
側に対し損害賠償請求をしたケース
概要
病院(相手方)に入院中の依頼者の父であるA氏は、要介護5の介護認定を受け、完全介護が必要な状態であった。A氏が食事中に看護師が席を外し、看護師がA氏のもとへ戻ってきたところ、心肺停止状態であるA氏を発見した。A氏は、救急搬送されたものの死亡が確認された。A氏の遺族(依頼者)は、相手方による安全配慮義務違反があると主張して、弁護士に依頼し、損害賠償請求訴訟を提起した。
争点
A氏の死因及び、相手方の安全配慮義務違反の有無
結論
司法解剖に付された結果、A氏の死因は本件食事の際に提供された食物を誤嚥したことによる窒息死と判明した。相手方は、安全配慮義務違反がなかったとして激しく争ったものの、最終的には安全配慮義務違反を認め、訴訟上の和解をした。
一言
相手方の過失を立証するだけの客観的資料を入手できるかどうかがポイントとなります。
本件は病院という密室で起こった事件であるため、本件事故発生前後の記録は病院が保管しています。したがって、被害者遺族が病院を相手どって訴訟を提起する場合、病院側に対し、その根拠となる本件事故発生前後の記録の提出を求める必要があるものの、その実現は容易ではありません。
また、裁判では、被害者側が客観的証拠を示して、病院側に安全配慮義務違反があったことを立証しなければならないため、たとえば亡A氏の看護記録や司法解剖の鑑定書等を入手し証拠として提出する必要があります。しかし、これらの書類も亡A氏や書類作成に携わった人間の個人情報保護の観点から簡単には開示してもらえず、一筋縄ではいかないのが現実です。
本件では、依頼者が、早期に私に依頼し、粘り強く対応した結果、客観的証拠の入手が可能となり、病院側の過失が認められました。亡A氏の名誉を回復し、真実を知りたいという依頼者の気持ちに寄り添うことができました。

その2相手方からの損害賠償請求と相手方に対する
未払代金請求とを一体解決したケース
概要
依頼者は、個人事業として、内装工事業を営む男性。相手方は、依頼者に対し、かつて内装工事を下請けさせていた内装工事業を営む法人。依頼者は、相手方にほぼ専従して、内装工事業をしていたところ、依頼者が別の依頼者からの業務を受託したことを相手方が知り、激怒した。その結果、それ以後、相手方は、依頼者に対し、下請け工事を発注しなくなったほか、下請け代金の一部である50万円を払わず、また、過去の下請け工事における依頼者の失敗により、相手方が肩代わりしていた損害が多数存在したなどと主張して、依頼者に対し400万円の損害賠償請求訴訟を提起した。
依頼者は、弁護士に依頼することで、相手方の請求に対し防御すると共に、反訴をして未払い代金の支払いを受けることを意図した。
争点
多額の請求を受けた場合の一体解決の内容
結論
100万円を依頼者が相手方へ支払うことで訴訟上の和解成立。
依頼者と協議をした結果、相手方からの請求について、相手方の請求額自体は過大ではあるものの、依頼者のミスとそれに伴い相手方に損害が生じたこと自体は事実であることから、相手方の主張内容を否定するのではなく、請求額をいかに減額させるかという方針となった。
裁判が進行する中で、相手方の提出した証拠が固い部分については、請求を認め、それ以外の点は争うという姿勢でいたところ、最終的には、依頼者の過失により相手方に150万円の損害が認められるため、この金額から未払報酬を相殺した結果、依頼者が100万円を相手方に支払うことで和解を成立させた。
一言
多額の請求内容の訴状を受け取ってショックを受ける方も多いと思います。私は、請求の本質と証拠関係を見極め、請求棄却を狙って徹底抗戦すべき事案か、証拠の不備や事実関係の相違を理由に請求額の減額を狙う事案か、請求内容はごもっともではあるものの、依頼者に資力がないなどの理由で、相手方の温情により減額や分割払いを認めてもらうべき事案かをまず判断します。
本件では、請求額の減額を求めるべき事案と判断しました。
私は、依頼者から聞いたことを聞かなかったことにすることはできません。事実は事実として尊重しており、弁護士として、事実を捻じ曲げたりは、決してしません。
客観的事実を基に、依頼者にとって、金銭関係や人間関係等に照らして、最も有利な解決ができる方法を常に意識して対応しております。
本件のケースでは、依頼者は、支払額が、当初請求された額の4分の1になったことを非常に喜んでおりました。

その3漏水事故被害を受けた依頼者が、工事業者に損
害賠償請求訴訟をしたケース
概要
依頼者は40代男性。マンションの3階で分譲マンションを所有し、第三者へ賃貸していたところ、上階の浴室リフォーム工事により、天井から漏水が発生し、貸室全体が水浸しの状態となった。
その結果、依頼者は修繕工事を余儀なくされ、部屋を借りていた第三者も別の場所へ転居せざるを得なくなった。依頼者は、上階のリフォーム工事を施工したリフォーム業者(相手方)と交渉し、1000万円を支払うことを内容とする契約書を締結したものの、相手方が、後日、かかる契約書が無効であると主張したため、依頼者は、弁護士に依頼して相手方に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
争点
損害賠償を約束した契約書の効力
結論
依頼者の主張に沿った内容の金額で裁判上の和解が成立した。
一言
交通事故などで、その場で念書を作成することがあることは、皆様も聞いたことがあると思います。自ら念書を作成した以上、原則として、当事者が、念書に記載したことを認めたという扱いになります。そのため、記載内容に誤りが全くないかどうかよく考えた上で、念書の作成の要否を判断する必要があります。