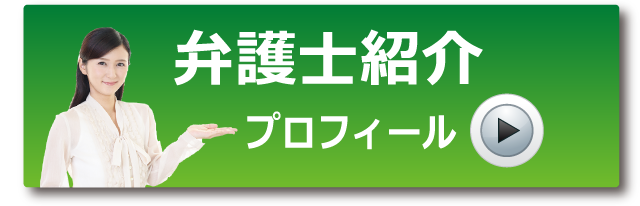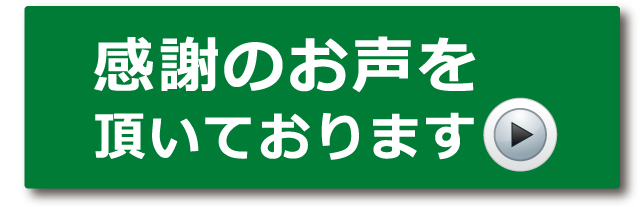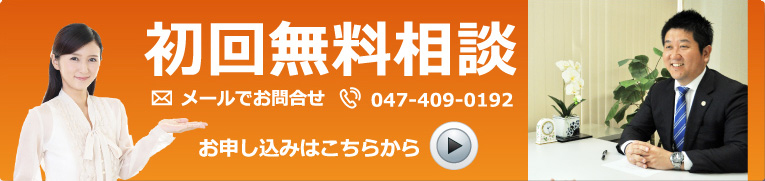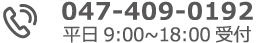![]()
労働トラブル(不当解雇など)


受ける相談として多いのは、不当解雇、違法な配置転換命令、違法な減給やパワハラ、セクハラなどです。労働トラブルは、他のトラブルよりも、相談者の生活に直結してしまう結果を招くことから、問題を解決する目的の部分で、金額が優先なのか、早期解決が優先なのか、雇用の維持が絶対条件なのかといったように、相談者の事情に応じて何が最適であるかを常に意識する必要があります。この点は、経験豊富な弁護士でないと、わからないことですので、当事務所の弁護士にご相談ください。

労働トラブル(不当解雇など)に関する弁護士費用
●協議・交渉(税込価格)
| 〇着手金 | 385,000円~440,000円 (事案に応じ変動) |
|
|---|---|---|
| 〇報酬金 | 385,000円~440,000円 (事案に応じ変動) |
金銭の請求(退職金、給与、未払い残業代、慰謝料等)を行う場合は、得られた経済的利益の11%の額が加算されます。 |
(税込価格)
●労働審判(税込価格)
| 〇着手金 | 495,000円~550,000円 (事案に応じ変動) |
|
|---|---|---|
| 〇報酬金 | 495,000円~550,000円 (事案に応じ変動) |
金銭の請求(退職金、給与、未払い残業代、慰謝料等)を行う場合は、得られた経済的利益の11%の額が加算されます。 |
※着手金については、協議・交渉から労働審判へ移行した場合は、その差額をお支払い頂きます。
(税込価格)
●訴訟(税込価格)
| 〇着手金 | 605,000円~660,000円 (事案に応じ変動) |
|
|---|---|---|
| 〇報酬金 | 605,000円~660,000円 (事案に応じ変動) |
金銭の請求(退職金、給与、未払い残業代、慰謝料等)を行う場合は、得られた経済的利益の11%の額が加算されます。 |
※着手金については、協議・交渉又は、労働審判から訴訟へ移行した場合は、その差額をお支払い頂きます。
(税込価格)
●備考(税込価格)
| 〇出廷日当 | 1回22,000円 | 左記料金は、千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部、東京地方裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。 |
|---|
(税込価格)
●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)
| 〇差出人がお客様名義の場合 | 33,000円~ |
| 〇差出人が弁護士名義の場合 | 55,000円~ |
(税込価格)
 当事務所で取り扱った
当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例事案の内容等については、
一部改変しております。
その1不利益処分をした会社に対し、労働審判により
損害賠償請求をしたケース
概要
依頼者は20代の女性。相手方は、勤務先の同族企業である。依頼者は、相手方の取締役や同僚から、「お前は使えない、頭が悪い、他に転職しろ。結婚したら仕事を辞めるのが一般的だから結婚するなら辞めてしまえ。使えない人間は結婚しても子を産む資格すらない」などといった、暴言や虐めの対象とされ、退職を執拗に迫られたものの、依頼者はこれに耐え、退職の意思表示をしなかった。そのうち、相手方は、依頼者に対し、雇用条件を正社員から非正規社員へ変更する内容に同意するよう執拗に迫った。
依頼者は、相手方による同意要求に対し拒否をしたものの、相手方は、依頼者の同意なくして、依頼者の身分を非正規社員へ変更することを強行した。
依頼者は、弁護士に依頼して、正社員としての地位の確認と未払いであった残業代の請求及び慰謝料を労働審判により請求したケース。
争点
相手方がなした不当処分及びパワーハラスメントを立証できるか。また未払い残業代及び慰謝料を請求できるか。
結論
依頼者の請求が全面的に認められた上で、相応な金額の解決金を受領し、解決しました。
一言
依頼者が、自身の主張を裏付ける証拠をきちんと保管していたこと、依頼者が受けた暴言の具体的内容を正確に記録していたこと等が決め手です。労働トラブルを抱えている方は、記録を残しておくべきです。
労働審判は、長くとも3回、期間としては1~2ヶ月程度で終了します。そのため、解雇処分、減給処分を受けているような弱い立場の労働者にとっては、通常の裁判手続よりも短期間で解決が見込めることから、通常訴訟よりも労働審判の方がより使用しやすい制度であるといえます。一方で、先に述べたとおり、労働審判は通常1回から3回で終了するため、裁判の進行に合わせて徐々に証拠を提出していくのではなく、まとめて一度に証拠を提出することにより、数少ない審判の場でいかに依頼者が不利益処分を受けていたかを審判委員に理解してもらう必要があります。
したがって労働審判申立書を説得力あるものにすることや、主張を裏付ける適切な証拠を提出することが大変重要です。ここが、弁護士の腕の見せどころでもあります。私は労働審判にも長けております。依頼者から詳細なヒヤリングをし、万全な準備をして審判に臨みますから安心してご依頼ください。

その2取締役の地位の不当解任を理由に会社に対し
損害賠償請求したケース
概要
依頼者は、会社(相手方)の取締役を務めていた。依頼者と相手方の代表取締役(相手方の大株主)との関係が徐々に悪化した結果、相手方の代表取締役は、依頼者に対し取締役を辞任するよう求めたものの、依頼者がこれに応じなかったことから、相手方の代表取締役が臨時株主総会を開催して依頼者を取締役から解任した。
依頼者の取締役としての残任期は、解任決議時点で、7年存在した。取締役解任決議自体は有効であるものの、解任には正当事由が存在しないため、依頼者は、弁護士に依頼して、相手方に対し、残任期分の報酬相当の損害賠償請求をしたケース。
争点
取締役解任には正当事由が存在するか。
結論
会社法339条2項では、株式会社は、株主総会決議によって何時にても取締役を解任することが許される一方で、任期満了前にその取締役を解任する場合には、解任に正当事由がない限り、取締役に対し解任により生じた損害を賠償しなければならないと定められている。
相手方は、依頼者の解任理由として、依頼者には責任感がないこと等を理由として挙げたが、これは主観的抽象的内容であったことから、判例の基準に照らして、正当な理由とは認められないと判断された結果、相応な期間に相当する役員報酬相当の損害賠償請求が認められた。

その3不当解雇をした会社に対し、労働審判により
損害賠償請求をしたケース
概要
依頼者は、介護資格を有し、相手方の業務に従事する男性。相手方の代表者は、依頼者のことを煙たく感じたことから、依頼者に対し転職するよう執拗に促していたところ、一旦は、依頼者も転職を真剣に検討することとなった。その後、条件が折り合わず、依頼者は、転職計画を白紙に戻したところ、相手方の代表者は、転職計画を白紙に戻した依頼者を嫌悪し、依頼者を解雇したため、依頼者が弁護士に依頼し、労働審判をすることになったケース。
争点
相手方による解雇処分が認められるか。
結論
依頼者の主張が全面的に認められ、相手方の解雇処分が無効であることを前提に、相当な額の解決金を会社が依頼者へ支払うことにより、本件が解決した。
一言
労働審判で労働者側が解雇処分の撤回を求める場合、労働審判では、「(雇用契約上の)地位の確認」という形式で、使用者に対し解雇処分を撤回し、元の職場に戻すことを請求します。もっとも、雇用関係の存在の確認という労働者の請求が認められたとしても、使用者と労働者の関係は既にこじれていますから、審判の結果、労働者が職場に復帰できたとしても、労働者にとっては働きにくい、使用者にとっては使いづらい空気が残ってしまいます。
したがって、実際の労働審判の場面では、使用者が相当な額の解決金を支払う代わりに、労働者と使用者の雇用契約の終了を認めるという形で解決することが多いです。